- 導入したいフローチャートが中々理解が得られない(東京都・歯科医師)
- 予算が合わないことが多い(言語聴覚士)
- 価格(言語聴覚士)
- 組織の理解、全職種から抵抗される(北海道・看護師)
- 金銭面、マンパワー面で導入が継続しない。多くの事業所が介入しており、制度上なかなかコンスタントに訪問できない。(小児の場合→)親御さんのメンタルが不安定でステップアップに至らないなど。(千葉県・言語聴覚士)
- 食環境の向上に関わる物品の購入が困難
- ドフィン(嚥下筋トレーニング機器)を導入したいが、予算の関係上厳しい(岩手県)
- 顧客のニーズ
- 受け手側の栄養リテラシーの低さ、栄養の重要さをご理解頂けない患者様多いという印象を受けているため、栄養士さんと一緒になり取り組みを続けている。(言語聴覚士)
- 人員不足
- 人員不足(福岡県・言語聴覚士)
- 人手不足による多職種連携の困難さ(兵庫県・言語聴覚士)
- 導入後うまく機能するかどうか心配 、協力いただけるか
- 他職種との連携
- 経営難により設備投資が出来ない
- 口臭を数値化する機械
- 介護士の口腔ケアに対する意識
- 時間の調整(歯科衛生士)
- ジェンティルスティム 収入にする方法を模索
- ベッドサイド内視鏡やジェントルスティムの導入(東京都)
- VEやVFができるように整えたいと思ったが、予算の都合で無理だと却下された。(東京都・言語聴覚士)
- ジェントルスティムの購入が予算的に難しかった(東京都・言語聴覚士)
- 予算、他職種の理解(神奈川県・管理栄養士)
- 現場職員の知識不足/新規事業への後ろ向きな姿勢
- 現在は対象者が少ないが、多くなった時に作業の見直しが必要(宮崎県・管理栄養士)
- 専門職が少なく、新たな取り組み始めるにも企画・準備か進めにくい(人手・時間不足)(山形県・言語聴覚士)
- 入所者様の数の多さ
- 他職種連携
- 価格(広島県・管理栄養士)
- 機器を導入したいが、予算面が課題となっている(言語聴覚士)
- 調理の工程調整(新潟県・管理栄養士)
- 物価高騰
- 介護現場にかける手間や、標準化がネックになることがあります(大阪府・歯科医師)
- 嚥下調整食4の硬さの調整が難しい。歯がないと噛めない硬さであることが多く、提供が難しい。(言語聴覚士)
- 予算がないため、実施する内容に制限がある
- 機器購入を依頼したが審査が通らなかった(言語聴覚士)
- VEは実施できる医師がいなかった(埼玉県・言語聴覚士)
- スタッフの皆さんの時間調整(長崎県・歯科医師)
- 衛生管理(愛知県・言語聴覚士)
- 多職種でどのように担当を決定するか
- 検査体制の充実
- 評価を行う病棟看護師の負担
- 人材
- 看護師の人員不足(長崎県・管理栄養士)
- 機能強化型認定栄養ケア・ステーションを更新せずに、訪問栄養の事業を縮小することが決まった
- 老健からの居宅良姜管理指導(Ⅱ)をとろうとしましたが、上司の理解が得られない。
- 国や自治体としての基準がないため施設に合わせる必要があり、委託給食会社としての基準を決めにくい
- 咳テスト導入のための方法が分からず導入に至っていない(院内の倫理委員会を通さなければならないのか、テスト施行の同意書が必要なのか、等分からないことが多く対応出来ていない)(宮城県・言語聴覚士)
- 導入したい機器と予算が合わなかった(大阪府・言語聴覚士)
- 時間の設定(言語聴覚士)
- 厨房委託業者との擦り合わせ(愛知県・管理栄養士)
- 機器の導入について、予算が合わない(言語聴覚士)
- 周知が難しかった(京都府・言語聴覚士)
- 予算(言語聴覚士)
- 周知:作成しても配るなどしないと見ない(管理栄養士)
- 人・もの・時間・経費(香川県・歯科医師)
- 栄養部員の臨床栄養知識の向上が図れない。(兵庫県・管理栄養士)
- 古くからの体質、知識不足、人員不足に伴う人員確保と時間確保、費用(歯科医師)
- 職員のやる気・意欲。取るだけの加算。自分のモチベーションの維持。業務量。(管理栄養士)
- NSTもしくはSSTを導入したいが医師・看護師不足によりチームが成り立たない。
- 職員それぞれの意識とスキルの違い(静岡県・管理栄養士)
- 指導者がいない(看護師)
- 献立の集約化 軟菜食の見直し
- 口腔嚥下栄養アセスメントシートを作成して、理解は得られてもなかなか浸透せず、苦労しました。(京都府・看護師)
- 予算が合わないこと、他職種での関わりが必要だが協力が得られない(言語聴覚士)
- VEでの嚥下回診をしたいが、協力してくださるフットワークの軽い医師がいない(大阪府・言語聴覚士)
- 職員の認識度や必要性の理解に差があること。
- 対象者抽出基準が無く基準構築が進まない(管理栄養士)
- 予算の関係で機器の導入が難しい。他職種との考え方の違い(すれ違いや認識違い)により技術伝達がスムーズにいかない(熊本県・言語聴覚士)
- 人員
- 管理栄養士の口腔ケアの関わり方
- 予算、人員(愛知県・管理栄養士)
- 給食委託会社の理解(神奈川県・管理栄養士)
- 栄養マネジメント強化加算の週3回のミールラウンドの記録は限られた時間の中でポジショニングから嚥下機能を観察するのは大変であること。(福島県・管理栄養士)
- なかなか機器の購入を承認してもらえなかった(言語聴覚士)
- ソフト食の導入が難しいこと(管理栄養士)
- 電気治療機器の購入(言語聴覚士)
- ポンプの追加導入に対する経費予算、看護師への知識普及(滋賀県・管理栄養士)
- 栄養士との連携がうまくいかない 嚥下造影検査を導入したいが予算的に厳しい
- 利益が減ってしまう
- 使用したい機器の対象者がごく一部となってしまい導入することのメリットが生み出せなかったこと。(東京都・管理栄養士)
- 全体への周知徹底(言語聴覚士)
- 予算、委託給食会社との調整が難しいです(鹿児島県・管理栄養士)
- 予算とマンパワー、病棟スタッフの理解がなかなか得られない(看護師)
- 機材が買えなかったので、外部の訪問歯科に協力を依頼した(福岡県・歯科衛生士)
- 作り手によって完成の状態が違うことがある
- 病棟スタッフとリハスタッフとの認識が異なっていた。(千葉県)
- 予算 人員(管理栄養士)
- 全職種の取り組みだったが、栄養士と言語聴覚士に皺寄せがきた(言語聴覚士)
- 食事介助をSTから、介護士さんにバトンタッチしたいが、介護士さんの嚥下障害の理解が低い、また食事介助方法をベッドサイドに掲示していて上手く伝わらず、誤嚥につながるケースが多い。そのためST下での食事から進まないケースが多い。(言語聴覚士)
- 人手不足
- 人員不足(介護士等)(言語聴覚士)
- 歯科と施設の口腔ケアに対しての温度差が大きい(神奈川県・歯科衛生士)
- リンクナースが機能しなかった
- 病棟の看護師ににより嚥下評価プロトコールを使用した評価に対する認識に差がある
- 看護師による嚥下スクリーニングがなかなか浸透しない
- 介護士に移行したくても、人員不足でできなかったり理解されない(言語聴覚士)
- 口腔ケアなど手技の統一化(奈良県・言語聴覚士)
- 他職種への協力依頼。特に看護師さんの説得は看護師さんにしてもらった方が他職種から言うよりも効果がありました
- 予算がないため、新規の機器導入などができない(茨城県・言語聴覚士)
- 苦味が強くて、一部の患者さんに不評。(群馬県・医師)
- 予算組(新潟県・管理栄養士)
- 嚥下調整食について委託業者との調整が困難。(埼玉県・看護師)
- 掲示しすぎて煩雑になった。(食事に限らず褥瘡予防や転倒予防の掲示があるので)(京都府・言語聴覚士)
- 日々の業務で手一杯で、新たな取り組みになかなか踏み出せない(言語聴覚士)
- 看護師さんの協力や同意(言語聴覚士)
- 急性期・回復期病院から退院時の情報連携が少なく、内容も酷いことが多い(管理栄養士)
- 全従業員に正しい知識や技術を周知することの難しさ。(言語聴覚士)
- 導入したい機器はあるが病院規模が小さく対象となる患者が限定的な為購入できない
- 看護師、医師の理解と周知
- 適応症例の選択
- 現場の理解が乏しく、認知度や実施方法の統一ができていない。検査を行っていても提供するものにとろみの有無が反映されていない。(埼玉県・言語聴覚士)
- 嚥下調整食(ソフト食・ハーフパワー食)導入について、時間と人材とコスト問題で採用できていない。(茨城県・看護師)
- 周知に時間がかかる
- グループ会社が変更となり、購入等に不便さがあり実行できないことがある
- 相談できる同職種がいなかったです。(熊本県・管理栄養士)
- 内視鏡の機器が高い。メンテナンスも含め。
- 予算(言語聴覚士)
- 介護スタッフが非協力的(福井県・歯科衛生士)
- 加算取得の勉強会などについて、多くのスタッフに理解度を深めるのにまだ時間がかかりそう
- 食事に関する意識の温度差(現在でも埋まっていないと思う)
- 主治医の認識の差異、見る視点の違い、重要性・意識の違いなど(言語聴覚士)
- 利用者と家族の理解、マンパワー、経済力、他事業所との連携など(東京都・管理栄養士)
- 栄養介入するにあたり、予算の都合で栄養補助食品を付けるのに限界がある
- Limited budget/staff; doctors need evidence; low patient acceptance.(言語聴覚士)
- Wi-Fi環境 保存を忘れると消える 保存すると容量が増えて手間とお金がかかる(茨城県・管理栄養士)
- 個人対応をもっと聞いてあげたいがマンパワーが不足している(管理栄養士)
- バイタルスティムもしくわジェントルスティムを購入したいが予算が合わない(看護師)
- マンパワー
- 他職種に取り組みを理解して貰う事。新しい取り組みは仕事が増えると思われ易い。
- 忙しい病棟業務のなかでは、摂食嚥下障害がある方へ統一した対応ができるようにしたシートを見てもらえない
- 予算が不足している(管理栄養士)
- とろみ食の方の飲み込みが悪いのを考え、ムース食に切り替えて行くこころみ
- 機器の購入に時間がかかる、他部署との調整(言語聴覚士)
- 機器の設定変更と全職員への周知等。既存のやり方を変えること。(埼玉県・管理栄養士)
- 予算
- 機器がない(管理栄養士)
- 予算と人材不足
- 衛生管理を遵守し時間内で調理する困難 委託調理師調理員への教育の難しさ
- 技量が統一できない。(京都府・調理師)
- ジェントル2台目を購入しようとしたが、予算的な面で見合わせている(言語聴覚士)
- 主治医の医療機関との連携(愛知県・歯科医師)
- スタッフの意識改革(鹿児島県)
- 口腔機能を測る機器が購入できない 予算がない
- 予算、マンパワー、スタッフの理解
- 日々変化しているので、実際に確認していない分乖離することがあった(北海道・言語聴覚士)
- 厨房の経年劣化による修繕費の増加(管理栄養士)
- 予算、人員不足(神奈川県・管理栄養士)
- 作業の所要時間(人員確保)(兵庫県・管理栄養士)
- マンパワー不足(兵庫県・看護師)
- 定期的なVF評価
- 口腔ケアの優先度(歯科衛生士)
- 人手不足
- 院長や理事長がコストばかり見るので安くないと通らない(大阪府・管理栄養士)
- 提供している食事の形態の各職種間の認識の統一が出来ていないこと
- 価格、情報の周知徹底
- 経営者の理解がない(管理栄養士)
- 予算 必要な患者の掘り起こし(歯科衛生士)
- 人手不足(愛知県・医師)
- 在宅ではリハビリ、看護師の介入回数が決められており、決められた回数の中でリハビリが行えないこともあり、機器を導入しても確認がとりずらかった。
- 導入したい機器と予算が合わなかった。
- 人手不足、経営難
- 調理師や食介助者(保育士・看護師)の知識と技術の向上について(栄養士)
- コストとシステム(埼玉県・管理栄養士)
- すべてにおける価格高騰(神奈川県・管理栄養士)
foodcare symposiumフードケアシンポジウム
当セミナーは終了いたしました
当セミナーは終了いたしました。
たくさんのご参加ありがとうございました。
事前にご登録いただいた方には、オンデマンドのご案内を配信しております。
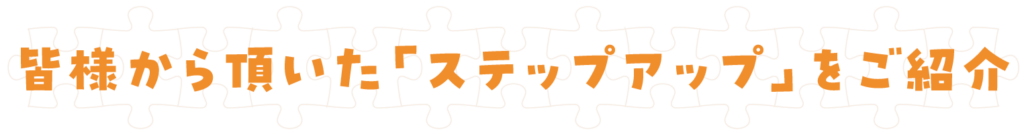
今回は、セミナー申込登録時に施設・病院での「ハードル」と「ステップアップ」をお伺いしております。
掲載の許可をいただいた皆様のコメントをご紹介いたします!
Q.所属する施設・病院等での新たな取り組みにおいて「ハードル」となったことは何ですか?
Q.所属する施設・病院等において取り組んだ「ステップアップ」したことを教えてください。
- GLIM基準(新たな低栄養診断基準)の活用(東京都・歯科医師)
- 昼食のみだったところ、朝食介入も始めました(言語聴覚士)
- 持続吸引メラチューブ(気道内の分泌物を継続的に吸引する医療器具)の導入(言語聴覚士)
- SST(摂食嚥下サポートチーム)設置、摂食嚥下障害治療や看護の標準化(北海道・看護師)
- ささやかでお恥ずかしいですが、ST(言語聴覚士)がいない事業所だったため「STに依頼するポイントがわかった(わかってもらえた)」ことです。(千葉県・言語聴覚士)
- ジェントルスティム導入(言語聴覚士)
- 食事介助スキルスコア (取り組み中)(東京都・管理栄養士)
- ユマニチュード(優しさと尊厳を大切にしたコミュニケーション)導入による多職種によるQOL(生活の質)の向上
- 軟飯を廃止し、酵素飯を導入(神奈川県・管理栄養士)
- 栄養カンファレンスの開催。毎週水曜日開催(岩手県)
- 栄養ケアステーション設立のための準備
- 栄養に限定するのであれば、ST(言語聴覚士)が患者様と栄養士を繋げる橋渡しの数を増やしていくこと。(言語聴覚士)
- 看護部と連携して、食形態の見直し中
- 現状維持できるよう、外国人スタッフでも対応できるように作業工程を見直しました。これからステップアップできるよう取り組みます。(福岡県・言語聴覚士)
- 嚥下内視鏡検査の再評価の実施、嚥下造影検査の立ち上げ(兵庫県・言語聴覚士)
- 現在フローチャートを作成中
- 全通院透析者の食形態や口腔内状態を記したプリントを個々のカルテ内に保管
- 利用者の口腔内を把握するために歯式(歯の種類や位置を番号で表す記録方法)を取った
- 口腔ケアについて施設向けに研修を開いた(歯科衛生士)
- 嚥下リハ強化のため歯科と連携
- VEの兵頭スコアは全職員理解できた(東京都)
- 今まで採用業務が手書きの宛名だったのをExcelなどを使用して時短にした。(東京都・言語聴覚士)
- 嚥下ステップアップフローチャートを作成した(東京都・言語聴覚士)
- 新たな食形態の導入/嚥下増粘剤の見直し
- 独自の嚥下質問シートを導入した(東京都・言語聴覚士)
- 離水しない全粥ゼリーの導入(宮崎県・管理栄養士)
- 低栄養状態のリスクの割合を月1回、可視化できるようにした。
- とろみ調整の法人内での統一化(広島県・言語聴覚士)
- 院内にフローチャートあり
- 嚥下調整食を全て手作りにした(新潟県・管理栄養士)
- 患者満足度の向上にむけた取り組みを行っています
- 独自の嚥下評価フローチャートを作成(言語聴覚士)
- スタッフ様からの質問が増えました
- 栄養情報共有
- 嚥下・VFの知識(言語聴覚士)
- 栄養評価にGLIM基準の説明をこまめに行うこと(大阪府・管理栄養士)
- 窒息予防を考慮した入院時質問票作成、院内周知、摂食嚥下サポートシステム構築(栃木県・看護師)
- 酵素の使用(管理栄養士)
- 評価の質を上げるためにVFやVEの取り組みを行った(埼玉県・言語聴覚士)
- ミールラウンドの内容をレベルアップした(長崎県・歯科医師)
- ポータブルVE機器購入のため入院時の嚥下フローに多職種で取組開始した
- 摂食機能療法の導入
- 入院患者の全員に病前の嚥下状態を評価し窒息のリスクを確認する体制ができた
- NSTチームの情報共有シートを作成した(長崎県・管理栄養士)
- 入院患者さんの退院後の食支援をスムーズに行うため、訪問栄養対象スクリーニングシートを作成運用し、業務フローチャートでの運用を始めた
- 利用者様に合わせて、可能な限り食事形態や食事量をカスタマイズして提供した。週1回以上の栄養モニタリングと週3回以上の食事観察。
- 栄養士教育のため、研修の中で食形態の説明を実施
- 管理栄養士と共に嚥下食の提供時間の調整を行った(午前・午後の早出し提供)(宮城県・言語聴覚士)
- 毎週、多職種で症例カンファレンスを行っている(言語聴覚士)
- 家族から本人の好きな食べ物を持ってきてもらい、必要な食事形態に調整して提供してあげる事(愛知県・管理栄養士)
- 病棟へのスクリーニング評価啓蒙活動(言語聴覚士)
- 看護師-言語聴覚士間で嚥下状態を共有し安全に摂食嚥下機能の向上を目指すために独自の連絡票を作成した(京都府・言語聴覚士)
- ジェントルスティム導入(言語聴覚士)
- 食事介助時の注意喚起を作成、それを元に簡単なマニュアルを作成(管理栄養士)
- 食事姿勢につき共通の清書を各職種で共有した。(香川県・歯科医師)
- リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定条件を確立した。(兵庫県・管理栄養士)
- 舌接触補助適応の患者に作製開始したこと。嚥下内視鏡検査を開始できたが、またハードルになった(歯科医師)
- 極わずかですが、協力体制。(管理栄養士)
- ジェントルスティムを導入を開始した。
- 誤嚥性肺炎の予防の取り組みとして、離床時に口腔ケアを行うようにした。(静岡県・管理栄養士)
- 看取り期にあるご利用者に対して、本人の望む食事、飲み物、匂い、味を届けている。
- 自費サービスで嚥下や食事支援を強化したい(看護師)
- 栄養管理手順書の見直し GLIM 基準への対応
- 校外での食事(やわらか食ペースト食について、飲食店との連携)
- 前の勤務先の病院で、口腔嚥下栄養アセスメントシートを作成したことがあります。(京都府・看護師)
- とろみの粘性をもう1段階追加しました(言語聴覚士)
- 少しでも有意義なVFになるように、毎回VF前カンファレンスを行うようシステム化した(大阪府・言語聴覚士)
- とろみの統一がなされていなかったため統一化を図った。
- NST立ち上げ始動(管理栄養士)
- 週一回の嚥下カンファレンス実施(継続中)、KTバランスチャートの導入(現在は使用していない)(熊本県・言語聴覚士)
- NST立ち上げ
- 近隣施設と連携し嚥下調整食一覧表作成(愛知県・管理栄養士)
- サルコペニアの嚥下障害の患者さんに対し、攻めの栄養管理(経管栄養のエネルギー量を✕35以上に)(神奈川県・管理栄養士)
- 加水ゼロ式調理法(神奈川県・管理栄養士)
- 食事形態と栄養補助食品の嚥下コード表を作成した
- 認知機能や摂食、嚥下機能の低下により食事の経口摂取が困難となっても自分の口から食べる楽しみを最期まで得られるよう、スクリーニング、モニタリング、カンファレンスの実施で多職種による支援の充実を図っている。(福島県・管理栄養士)
- 今年度からジェントルステイムを導入した(言語聴覚士)
- これからステップアップできるようになりたいので今回先生方のお話聞きたいです
- 摂食嚥下回復体制加算の算定率向上の取り組み(言語聴覚士)
- 経腸栄養から早期に経口摂取へ移行あるいは必要栄養量の充足に向けてプロトコルを作成して注入トラブルによる廃用悪化の防止を図った(滋賀県・管理栄養士)
- 置き換え食の導入
- 栄養改善を図ることに加え個別性に対応するために、補助食品の固定化をなくした。(東京都・管理栄養士)
- 嚥下診療ガイドラインの策定、嚥下スクリーニングの導入(言語聴覚士)
- 支援部、リハ部、看護部、中間管理職の方々と食事検討委員会が立ち上がり、栄養食事の面について話し合いができるようになってます(鹿児島県・管理栄養士)
- 摂食嚥下障害患者様の入院時の食事選択のフローチャートを作成した(看護師)
- 摂食嚥下の評価をより確かなものにするために、三位一体の取り組みに嚥下内視鏡検査をプラスして検査も結果の数字だけではなく、検査実施に多職種が集まって行います。より安全に嚥下していくための取り組みです(福岡県・歯科衛生士)
- 流動の粥をミキサー粥からスベラカーゼを使ったゼリー粥に変更した
- 咽頭マイク・とろみ段階の調整・医療、介護栄養情報連携
- 行事食として嚥下食のたこ焼きを提供、大好評を得ました!(愛知県・理学療法士)
- 口腔栄養リハビリテーション加算を開始した(言語聴覚士)
- 利用者の口腔状態を把握し一覧にまとめ、口腔ケアの啓蒙を行った(言語聴覚士)
- 施設の利用者様の口腔ケアをしているところを出来るだけ見て頂くようにして、少しでも口腔ケアの重要性を知ってもらうように努めてます(神奈川県・歯科衛生士)
- NSTのリンクナースを配属した。
- 全病棟共通の嚥下評価プロトコール表を作成した
- コーンスープ味など甘くない栄養補助食品を採用した
- とろみの作り方マニュアルを作成した。(奈良県・言語聴覚士)
- 嚥下回診という嚥下チームを看護師さんと立ち上げました
- 常勤職員が増えた(茨城県・言語聴覚士)
- 経管栄養管理方法を改善した(鹿児島県・管理栄養士)
- VFの造影剤をヨード系に変更した。(群馬県・医師)
- さらなる症例共有(新潟県・管理栄養士)
- 経口摂取プロトコールの作成(埼玉県・看護師)
- 各勤務帯でばらつかないよう誤嚥予防のために姿勢や介助方法の統一を図るためポスター提示している(京都府・言語聴覚士)
- 施設内で独自の評価用紙を作成し、誤嚥や窒息リスクの高い方の評価に役立てている(言語聴覚士)
- KTチャートを使用した摂食機能療法の推進(言語聴覚士)
- 訪問看護の言語聴覚士と連携して訪問栄養実施中(管理栄養士)
- 経口摂取開始のフローチャートを作成した。(言語聴覚士)
- 低栄養を防ぐためにパワーライス全粥を提供している
- 院内発症の誤嚥性肺炎予防のため嚥下フローを作成した
- 安全な食事開始に向けて改訂水飲みテストの検査を全症例に開始した。(埼玉県・言語聴覚士)
- 特養の栄養ケア計画書を作成しました。(熊本県・管理栄養士)
- 施設との連携。
- 食べる院内デイの開催(言語聴覚士)
- 口腔衛生管理が習慣化するように委員会と様々な取り組みを行っている(福井県・歯科衛生士)
- NST介入時、OHATを用いて評価しカルテ内共有をしている。リハ栄養口腔連携加算取得にあたり、多職種勉強会を実施。
- 施設なのでNSTといった取り組みはできていないが、必要時にはチーム医療を意識した声掛けを行うようになった。(今まで声をかけないと食事場面で来てもらえなかったので)
- 摂食嚥下支援チームの発足 「摂食嚥下障害早期介入フロー」の作成(言語聴覚士)
- (在宅)ヘルパーとの連携により、酵素入りお粥を使用したミキサー食で食べたいものが食べられた(東京都・管理栄養士)
- 経口維持・経口移行支援のマニュアルを作成した 入所者全員へGLIM基準での低栄養診断を行い、栄養カンファレンスを行っている
- Coordinate with nurses, use low-sugar nutrition based on glucose, monitor before/after training.(言語聴覚士)
- 関係者と連携を図りやすくするために、摂食相談の様子を短く動画にして保護者の携帯にその場で送るようにした(茨城県・管理栄養士)
- NST内に摂食嚥下チームを作り活動を始めている(管理栄養士)
- 嚥下外来を始めた。摂食嚥下支援チーム委員会立ち上げ。(看護師)
- 多職種での嚥下評価
- 入院後早期の摂食嚥下スクリーニング〜VEに繋げるルートの作成
- 摂食嚥下障害がある方へ統一した対応ができるようにしたシートの作成、導入。
- 看護学生への教育(大分県・管理栄養士)
- 肺炎患者の評価の強化にむけて取り組み中(言語聴覚士)
- とろみの基準と施設内の呼び方を学会分類に合わせ統一した。(埼玉県・管理栄養士)
- 栄養状態改善(管理栄養士)
- これまで市内管理栄養士と連携し嚥下調整食マップを作成した ゼロ加水に取り組みはじめた
- やっとソフト食の導入された(青森県・看護師)
- 口腔ケアチームを発足し、週二回のラウンドやオーハットでの評価を行い看護師の口腔ケアに対する意識を高めた(言語聴覚士)
- 新たな摂食嚥下訓練ステップチャートを計画(愛知県・歯科医師)
- 利用者の栄養改善を図るための多職種共同フロチャートを作成した
- 加算の算定(栄養マネジメント強化加算、経口維持加算算定)(鹿児島県)
- 近郊病院の提供している食事内容を聞き取りし、嚥下調整食表を作成・当院で使用している(北海道・言語聴覚士)
- ソフト食の導入(管理栄養士)
- 摂食・嚥下障害患者が経口摂取獲得のためのフロー(兵庫県・看護師)
- ジェントルスティムEX導入
- 摂食機能療法の介入
- 食上げのフローチャート作成した(歯科衛生士)
- 多職種の摂食嚥下に対する意識が高まった
- 嚥下調整食分類の勉強会を行った。
- 口腔リハビリの為のアプリの使用開始(歯科衛生士)
- 栄養カンファレンスに取り組んだ(愛知県・医師)
- 施設入所中の方にジェントルスティムのレンタルをご提案し導入に至った。
- 食事摂取基準の見直し
- 巡回STと連携を図り嚥下調整食給食の段階的食形態の見直しを行った。(栄養士)
- 直営化により給与栄養目標量の見直し、食事形態の変更(神奈川県・管理栄養士)
- 経口移行を進めた(神奈川県・管理栄養士)
ABOUTフードケアシンポジウムとは?
フードケアシンポジウムは、全国各地でご活躍されている医療・介護従事者の方より『摂食嚥下へのアプローチ』について「栄養」 「口腔ケア」 「リハビリテーション」の3つの視点から日頃の取組みや臨床事例を講演いただくイベントです。
診療報酬・介護報酬改定でも「自立支援・重度化防止のための効果的なケアを提供する観点から、多職種による一体的なリハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理が実施されることが望ましい」という方針が示され、3つの分野での取組みがより重視されていくと考えております。
各分野の事例が患者・ご利用者さまのQOL向上や医療・介護現場での課題解決に繋がれば幸いです。
LOGOフードケアシンポジウム ロゴ

栄養・口腔ケア・リハビリテーションそして フードケアが1つになり、
医療・介護における「多職種連携」を推進したいという想いを込めました。
院内や地域の枠を超えて、フードケアシンポジウムが 全国各地のつながりのきっかけになれば幸いです。
OVERVIEW開催概要
第4回のテーマ
“今まで通り”からのステップアップ
~摂食嚥下にまつわる挑戦~
物価高騰・人手不足・働き方改革・診療報酬、介護報酬改定など、医療と介護を取り巻く環境はまさに激変していると考えます。
そんな状況下で現状をより良くしようと取り組まれている挑戦についてお話しいただく予定です。
| 開催日時 | 2025年11月29日(土) 13:30~16:40 |
| 開催方法 | オンライン オンデマンド配信あり ※オンデマンド視聴のご案内は、申込者限定でお送りします。 |
| 参加費用 | 無料 |
| 定員 | 1,000名 |
| 座長 | スワローウィッシュクリニック 院長 |
PART 1第一部
「栄養」「口腔」「リハビリテーション」分野の切り口から臨床現場で活躍する先生方にご講演いただきます。
栄養
田川 佳奈子 先生
-

長崎リハビリテーション(長崎県)
- 栄養士
スベラカーゼお粥ゼリーの素を使った嚥下調整食への新たな取り組み
~障がい者支援施設における実践と加水ゼロ式調理法の可能性~- 当施設では、咀嚼・嚥下に課題を抱える利用者様に対し、5つの食形態に分類した食事提供を行っている。高齢者とは異なるニーズを持つ障害者の方々への対応において、従来のとろみ調整食品使用による嚥下調整食の不安定さや、調理員への指導方法に課題を抱えていた。スベラカーゼお粥ゼリーの素を導入したことで、より安定した嚥下調整食の提供を実現した。スベラカーゼお粥ゼリーの素がとろみ調整食品以外の選択肢として、調理現場での活用方法や導入までの経緯を共有し、「現場で使える嚥下調整食」をテーマに、病院・福祉施設での食支援の質を高めるヒントを紹介する。
-
保田 祥代 先生
-

刈谷豊田総合病院(愛知県)
- 言語聴覚士
摂食嚥下障害患者の目標設定
~嚥下訓練食品(コード0j)をどう活用する?~- 初めて摂食嚥下障害患者様を担当した時、「この患者さん食べれるようになる?」「どのくらいで食べれるようになる?」と問われ、明確に応えることができず困惑したことを今でも鮮明に覚えている。摂食嚥下障害患者様の目標設定は、今後の治療方針や退院先を検討する上で重要である。当院では咀嚼・嚥下調整食としてゼリー食を提供している。どのように目標設定し、嚥下訓練食品(0j)をどう活用しているか報告する。
口腔ケア
坂本 英世 先生
-

まちだ丘の上病院(東京都)
- 言語聴覚士
言語聴覚士が行う口腔ケアと療養型病院全体で取り組む嚥下障害へのアプローチ
- 療養型病院である当院に入院している患者の大半は、絶食の状態で転入院してくる。中には「経口摂取は望めない」と言われてくるケースも少なくない。そのような中、2024年8月から2025年7月までの間に入院をしていた158名の患者のうち、22名が絶食から3食経口摂取に移行した。「食べるための口作り」を目指した言語聴覚士ならではの口腔ケアと、病院全体で「食べる支援」を行っている当院の取り組みを紹介する。
-
上田 隆介 先生
-

レアール訪問歯科横浜鶴見院(神奈川県)
- 歯科医師
口腔ケアによる患者満足度と病院スタッフの意識改革に関する調査結果について
- 口腔ケアの重要性は感じてはいるが、忙しい中では現実的でないと感じている方は多いのではないでしょうか。口腔ケアの障壁となるものは何か、病院スタッフの声と歯科の取り組みの結果を報告する。口腔ケアの患者満足度への影響、病院経営への影響について等、多角的な視点から発表する。
リハビリテーション
- 中村 美瑠 先生/小田 奈津希 先生
-

介護老人保健施設 野洲すみれ苑(滋賀県)
- 言語聴覚士
老人保健施設でのジェントルスティム・EXの導入と活用~最後まで口から食べるための挑戦~
- 当施設では嚥下障害を抱え誤嚥リスクの高い方の入所が増えている。昨年5年ぶりに言語聴覚士を採用し、今年から2名体制で支援が可能になった。誤嚥性肺炎の予防や嚥下機能の維持向上に力を入れ、「最後まで口から食べる喜び」を支えるよう取り組んでおり、その一環として「ジェントルスティム・EX」を導入した。今回はジェントルスティム・EXを導入した経緯と施設での活用について報告する。
天白 陽介 先生

- 名古屋掖済会病院(愛知県)
言語聴覚士
ICUからお届け!人工呼吸管理と摂食嚥下機能に関するおはなし~電気刺激療法の可能性を添えて~
- 集中治療室は日々重症患者に対して集学的な治療が為される過酷な環境である。重症患者では全身状態や高侵襲な治療が原因となり摂食嚥下機能障害が好発である。しかし、摂食嚥下機能障害の専門家である言語聴覚士(ST)が集中治療室に常駐している施設は全国でわずか2%と大変少ない。本公演では集中治療領域を専門とするレアなSTが人工呼吸管理と摂食嚥下機能障害の関連及び電気刺激療法の可能性に関してお話しする。
PART 2第二部
座談会
テーマ:ステップアップするためにどうやって理解を得る?
座長 金沢 英哲 先生と、第一部に登壇された先生方によるトークセッションを行います。
製品の新規導入、業務フローの変更などの「ステップアップ」には関係者の理解が必要になると思います。よくあるハードルと、その乗り越え方について座長と登壇者にて意見交換します。
座長
スワローウィッシュクリニック
- 院長 医師 金沢 英哲 先生
演者
第一部登壇者の皆様
DIGEST過去の登壇者様
※開催当時の情報です

第1回
開催日 2022年11月12日Sat
テーマ 摂食嚥下機能低下に対するアプローチ ~多職種の輪を広げよう~
栄養
 | 特別養護老人ホーム 白熊園 川原 瞳 様 「経営的視点から考える厨房運営 ~ニュークックチル導入に至る過程と現状~」
|
 | 今津赤十字病院 内海 斉美 様 「加水ゼロ式調理法(加水代わりにお粥ゼリーを用いたコード2相当のペースト食)の導入から1年」
|
 | 医療法人社団まごころ 宮阪 美穂 様 「在宅での食支援ポイント ~多職種チーム・もぐまごの活動~」
|
口腔ケア
 | JA鹿児島厚生連病院 吉良 理美 様 「当院における口腔ケアへの取り組みとジェントルスティムの試用結果について」
|
 | 朝日大学 多田 瑛 様 「口腔、咽頭のトータルケアを考える」
|
 | 介護老人保健施設 末広荘 田口 義久 様 「訪問リハにおける口腔ケアの重要性」
|
リハビリ
 | 西山病院 山本 梨花子 様 「慢性期病院におけるジェントルスティムの導入と活用 ~口から食べるを叶える~」
|
 | 初台リハビリテーション病院 井上 典子 様 「回復期リハビリテーション病棟におけるジェントルスティムの活用状況について」
|
 | 佐野厚生総合病院 小林 佳子 様 「摂食嚥下リハへの多職種アプローチ~摂食機能療法の算定実施を含む~」
|

第2回
開催日 2023年12月2日Sat
テーマ ワタシたち“摂食嚥下”のために「コレ」してます!
栄養
 | ないとうクリニック 伊藤 清世 様 「委託給食会社と取り組む食形態調整」
|
 | 赤羽病院 俊成 桃香 様 「多職種連携で実現した食形態ととろみつき飲料の見直し」
|
 | 越谷市立病院 奥田 朋子 様 「多職種との連携で嚥下調整食提供を実現した一例」
|
口腔ケア
 | 井野辺病院 山口 泉 様 「回復期リハビリテーション病棟の『食べたい』を支える」
|
 | 岡山済生会総合病院 園山 愛弓 様 「口腔支持療法としての口腔保湿ジェルの可能性を探る」
|
 | Taste&See 西 依見子 様 「口腔保湿ジェルを活用した口腔ケアの指導方法について」
|
リハビリ
 | 大分大学医学部附属病院 松浦 祐也 様 「急性期病院における干渉電流型低周波治療器の活用状況」
|
 | 出雲徳洲会病院 三谷 俊史 様 「干渉電流型低周波治療器が咽頭知覚に与える影響の検討」
|
 | 海南医療センター 伊藤 僚祐 様 「経皮的干渉波電気刺激の使用における病棟との連携」
|

第3回
開催日 2024年11月23日Sat
テーマ 摂食嚥下と日々のやりくり ~ヒト・モノ・カネ・情報・時間ってどうしてる?~
栄養
 | 泉保養院 小林 真美 様 「嚥下調整食の見直しで人手不足を解消」
|
 | 松田病院 鈴木 奈緒子 様 「日々の情報共有と多職種連携で支える当院の栄養ケア」
|
口腔ケア
 | 新吉塚病院 辻 恵子 様 「『口腔』を味方につける ~今こそ情報共有~」
|
 | 合同会社 Comer 大城 清貴 様 「効果的・効率的な食支援に必要なこと」
|
リハビリ
 | 蒲田リハビリテーション病院 小笠原 彩華 様 「法人内での情報共有 ~干渉電流型低周波治療器の活用に向けた取り組み~」
|
 | 札幌麻生脳神経外科病院 源間 隆雄 様 「『リハビリ・栄養・口腔』を意識して ~短期間で成果をあげてより良い環境を作る取り組み~」
|
OMAKEおまけ
過去公開したCM
過去のフードケアシンポジウム内の休憩時間で公開したCMです









